全国40支社・140名以上の
ライフ アカンパニスト(Life Accompanist)が
いつもそばにいます。
※アカンパニスト(Accompanist)とは
伴奏者・ともに楽しみ、ときに支援し、ともに喜ぶ人
Life Accompanist は人生の伴奏者を意味します。

戦後半世紀以上が過ぎ、高度経済成長、
バブル崩壊後失われた10年、15年を経験したわたしたちの暮らしは、
混沌という大海に投げ出されたことに等しく、
一人ひとりが、進むべき道を自ら考え、
航海に出て行かなければならない時代となりました。
わたしたちFPエージェンツは、
お客様の人生におけるさまざまなリスクに対処すべく、
人生という航海の羅針盤を提供いたします。
「Always beside you…FPAgents」 を理念に、
お客様と大切なご家族をお守りするエージェントとしてお仕えし、
いつもそばにいる身近な相談役を目指します。
- 本社 –
千葉県
千葉市花見川区
東北エリア
6支店
関東甲信エリア
11支店
東海北陸エリア
8支店
関西エリア
7支店
九州エリア
8支店
全国40支社・140名以上の
ライフ アカンパニスト(Life Accompanist)が
いつもそばにいます。
※アカンパニスト(Accompanist)とは
伴奏者・ともに楽しみ、ときに支援し、ともに喜ぶ人
Life Accompanist は人生の伴奏者を意味します。
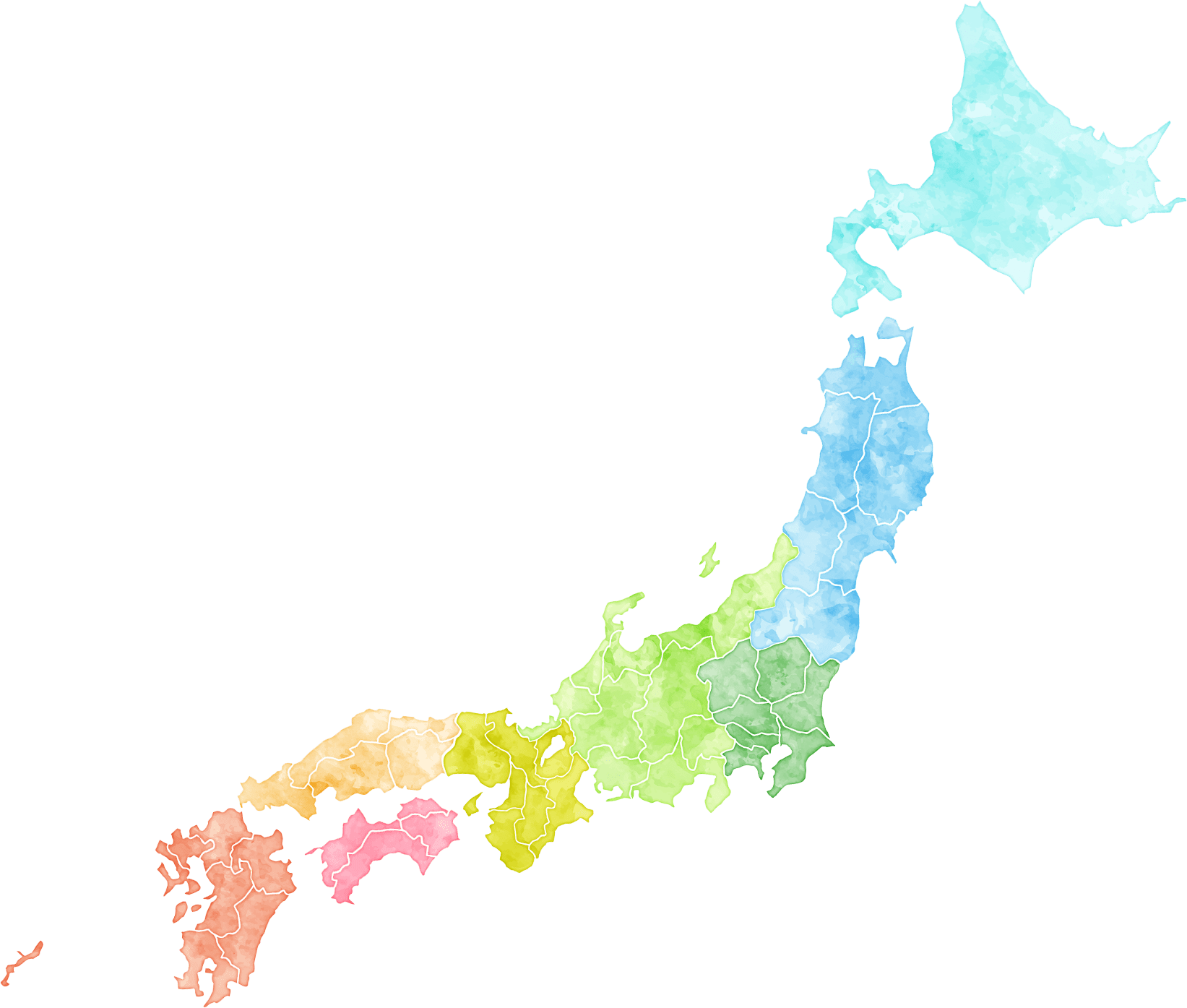
安心と希望に満ちた地域を増やす
安心と希望を届けるだけでなく、人と人をつなぎ安心の輪をつくる
安心だけでなく希望を提供する。そして世代を超えて守り続ける

営業時間9:30~17:30/定休日:土日祝